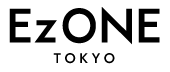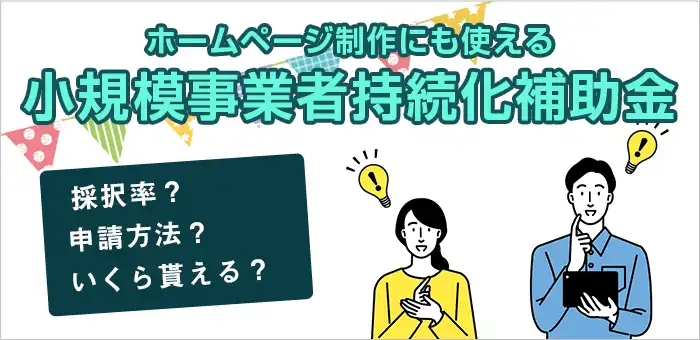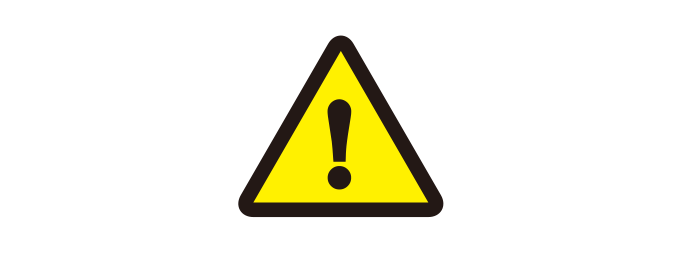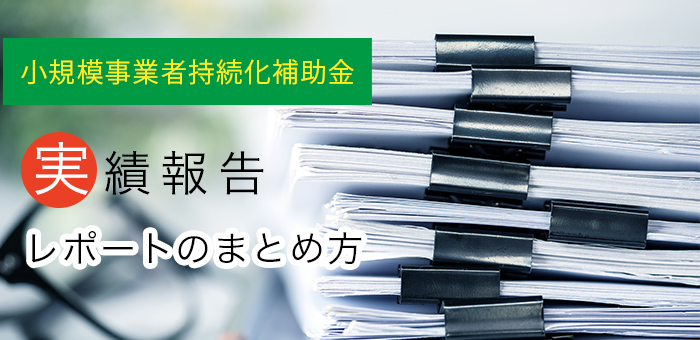「小規模事業者持続化補助金」は、全国の商工会議所が主催する補助金の制度です。小規模事業者を対象に、事業計画書に基づいて採択された場合、一定の経費補助が受けられる制度になります。
この記事では、製品やサービスをPRするための広告宣伝費にも使える小規模事業者補助金について、概要・書類作成方法・申請方法・スケジュール等についての詳しい内容を解説します。
目次
小規模事業者持続化補助金とは?
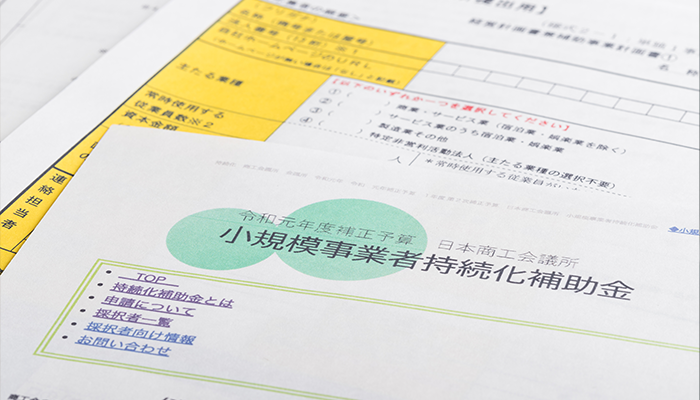
小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者が、「販路開拓」や「業務効率化(生産性向上)」のための企業活動でかかる「経費の一部」を国が支援してくれる制度です。
具体的には、ウェブサイト制作や、販路開拓のための広告宣伝費、生産性向上のための設備投資、新製品開発のための研究開発費などで使う経費にかかった費用の約2/3(赤字企業で賃上げ特例を選択した場合は3/4)を補充してくれる制度になります。
例えば、集客するためにポスティングでビラを配ったり、広告を出稿したり、設備投資や機材購入でかかった経費が全体で75万円の場合、そのうちの50万円(全体の2/3)を補助金によってまかなえるため、自己負担金を少なく新規事業や業務改善に取り組めるといった内容になります。(申請する枠によって補助金で受け取れる上限額が変わります)
申請すれば誰でも補助金が受け取れるわけではなく、「事業計画書」の作成や「申請書類一式」の準備が必要で、「採択」されて初めて、補助金を使うことができる権利を得ることができます。
令和7年からの応募枠について
昨年までは、「さまざまな条件によって補助金額の上限が変わる新設枠」が用意されていましたが、今年から基本補助上限は50万円、さらに「従業員に対して賃上げできる企業」に対しては補助金額が増額される内容に変更されました。
また別途、従業員を雇用していないような、創業3年以内の新規事業主には、補助金上限200万円(特例を活用した場合250万円)までの「創業型」も用意されました。こちらは第1回の応募枠が新しく開始されたため、創業3年以内で起業した方はこちらが狙い目です。(応募の前に、特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書を得る必要があります。詳しくは公式HPを確認してください。)
| 類型 | 一般型通常枠 | 創業型 |
|---|---|---|
| 補助率 | 2/3(赤字企業で賃上げ特例を選択した場合は3/4) | 2/3 |
| 補助上限 | 50万円(特例を活用した場合、最大250万円) | 200万円(特例を活用した場合、最大250万円) |
| インボイス特例 | 補助上限額に追加で+50万円上乗せ (インボイス特例の要件を満たしている場合) |
|
| 賃金引上げ特例 | 補助上限額に追加で+150万円上乗せ(賃金引上げ特例の要件を満たしている場合) | |
| インボイス特例 + 賃金引上げ特例 | 補助上限額に追加で+200万円上乗せ(どちらの特例の要件も満たしている場合) | |
| 申請要件 | 小規模事業者に該当すれば誰でも可能(ただし、過去開催分で採択済みの事業者は対象外となる場合あり) | 開業日が公募締め切り日から起算して過去3年以内であること |
インボイス特例の要件について
2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった又は免税事業者であることが見込まれる事業者及び2023年10月1日以降に創業した事業者のうち、適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者であること。(2023年9月30日前は免税事業者であった、または2023年10月1日以降に創業し、インボイスに対応した事業者)
賃金引上げ特例の要件について
補助事業の終了時点において、事業場内最低賃金が申請時の事業内最低賃金より+50円以上であること。実績報告時に、賃金台帳の写しと、労働条件通知書(雇用契約書)の写しの提出が必要。
(過去開催分)「一般型」と「低感染リスク型ビジネス枠」
2022年(令和4年)頃の小規模事業者持続化補助金には、「一般型」と「低感染リスク型ビジネス枠(新型コロナ対応枠)」の2種類がありました。回を重ねるごとに内容が更新され、現在は「一般型(通常枠)」を基本として、条件によって補助金上限が上乗せされる内容になっています。
申請対象となる事業者の条件
対象となる小規模事業者は、従業員数が5名以下または20名以下(宿泊・娯楽・製造業の場合)であることが条件です。それ以上の規模の事業者の場合、別の助成金制度を利用する必要があります。
通常は、個人事業主や営利法人(株式会社、合資会社、合同会社等)が該当します。医師や個人の林業・農業者、一般社団法人等は該当しません。
また、直近過去3年分の課税所得の平均額が15億円を超えていないことや株式保有比率などの制限もあります。
公募のスケジュールについて
公募のスケジュールは下記の表のとおりです。2024年5月締め切り以来、1年ぶりに公募が再開されています。
| 回号 | 一般型 第17回 または 創業型 第1回 |
|---|---|
| 締切り※ | 2025/06/13(金) |
| 事業支援計画書(様式4)発行の受付締切 | 2025/06/03(火) |
| 採択結果 | 2025年8月頃 |
| 実績報告書(事業完了報告)の提出期限日 | 2026/08/10(月) |
※締切りの1週間前までに、申請書類一式を用意し、所属する商工会議所に「事業支援計画書(様式4)発行」を依頼する必要があります。
※申請して不採択になった場合でも、次回の申請でまた申し込みすることが可能です。
※gBizIDを発行していない場合、発行までに3週間ほど時間がかかるため早めの対応がオススメです。
| 回号 | 第08回(締切り) | 第09回(締切り) | 第10回(締切り) | 第11回(締切り) | 第12回(締切り) | 第13回(締切り) | 第14回(締切り) | 第15回(締切り) | 第16回(締切り) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切り | 2022/06/03(金) | 2022/09/20(火) | 2022/12/09(金) | 2023/02/20(月) | 2023/06/01(木) | 2023/09/07(木) | 2023/12/12(火) | 2024/03/14(木) | 2024/05/27(月) |
| 採択結果 | 2022/08/31(水) | 2022/11/25(金) | 2023/02/06(月) | 2023/04/27(木) | 2023/08/23(水) | 2023/11/27(月) | 2024/03/04(月) | 2024/06/05(水) | 2024/08/08(木) |
| 実績報告書(事業完了報告)の提出期限日 | 2023/03/10(金) | 2023/06/10(金) | 2023/08/10(金) | 2023/09/30(土) | 2024/04/30(火) | 2024/07/31(水) | 2024/09/10(火) | 2024/10/31(木) | 2024/11/14(木) |
補助金の「採択率」とは?
採択率とは、申請件数に対して審査が通った申請者の割合のことをいいます。2021年から始まった採択率の結果を見ると、次のようになっています。
| 結果 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第7回 | 第8回 | 第9回 | 第10回 | 第11回 | 第12回 | 第13回 | 第14回 | 第15回 | 第16回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申請者数 | 7,827件 | 10,205件 | 8,056件 | 8,243件 | 12,738件 | 9,914件 | 9,339件 | 11,279件 | 11,467件 | 9,844件 | 11,030件 | 13,373件 | 15,308件 | 13,597件 | 13,336件 | 7,371件 |
| 採択者数 | 7,308 | 12,478 | 7,040 | 7,128 | 6,869 | 6,846 | 6,517 | 7,098 | 7,344 | 6,248 | 6,498 | 7,438 | 8,729 | 8,497 | 5,580 | 2,741 |
| 採択率 | 90.9% | 65.1% | 51.6% | 44.2% | 53.9% | 69.1% | 69.8% | 62.9% | 64.0% | 63.5% | 58.9% | 55.6% | 57.0% | 62.5% | 41.8% | 37.2% |
数字を見ると、回号ごとにバラつきはありますが、平均的に50%~70%と高い採択率になっています。有識者のアドバイスを受けながら、事業計画をしっかり作り準備をすれば、採択される可能性は十分にあります。
独自システムが導入された第15回から、採択率が非常に下がっています。申請内容は通ったものの書類不備等の理由で不採択になった事業者が増えた可能性が高く、今後申請時には注意が必要です。オンライン申請に苦手意識がある場合、申請代行を行ってくれるところを探しておくと良いかもしれません。
小規模事業者持続化補助金に申請するために必要なもの
小規模事業者持続化補助金の経費として認められるものは「小規模事業者が地道な販路拡大をするために必要な費用」が対象です。何でも経費として認められるわけではないので、事前に「事業計画書」を作成し、経費の内訳をよく検討しておく必要があります。(採択後に、見積書、契約書、納品書、支払い証明書などを1つ1つ用意する必要があり大変です)
また、申請に際しては、納税証明書や事業証明等の公式書類準備に加え、電子申請のためのgBizIDの取得が必要です。
※第15回開催から、jGrantsではなく「独自システム」による申請に切り替わりました。Gビズアカウントは引き続き利用します。
申請可能な予算項目について
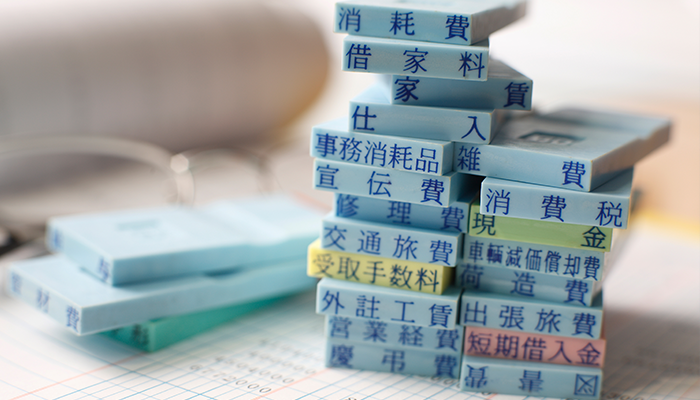
商工会議所の公式ホームページによると、経費として申請可能な項目には次のようなものがあります。
【対象となる事業経費の例】
- ①機械装置等(単価が50万円未満の資材)
- ②広報費(チラシ・カタログ・紙媒体広告・看板・DM発送費等)
- ③ウェブサイト関連費(ホームページ作成・インターネット広告・動画作成・SEO対策・システム開発・SNS広告等)※補助金確定金額の1/4までが上限
- ④展示会等出展費(展示会出店にかかる経費全般)
- ⑤旅費(展示会出展や、資材調達のための宿泊代、飛行機代、電車代等)
- ⑥新商品開発費(新商品開発のための原材料費・パッケージデザイン費)
- ⑦借料(機器・設備等のリース料・レンタル料)
- ⑧委託・外注費(事業に必要で自らが実行することが困難な業務)
補助金額50万円を基本として考えた場合、「(新規)事業に必要な投資」に加え、「販路拡大のための計画」を組み込んで75万円で実現できる計画を用意する必要があります。さらに、補助事業を検討するためのアドバイザーを外注した場合、10万円~の成果報酬を求められることが多いです。予算を多めに用意し、あくまで「補助金は補助金」という位置づけで取り組むと実現しやすいプランが計画できそうです。
また、経費項目は、事業計画に従って「必ず必要となる経費」であることが求められます。具体性のない経費では、後から必要となる証跡の提出が困難になるため、見積り書がとれる場合は事前に用意しておき、採択後の実績報告のことも考えた上で書類を準備しておく方が良いでしょう。
ウェブサイト関連費の経費の考え方
ホームページ制作やシステム開発、ECサイト構築、デジタル広告運用で使える費用は、補助金総額の1/4が上限に定められています。補助金を満額で申請した場合、次の表ような組み合わせになります。
「ウェブサイト関連費以外の経費」には、広告宣伝費を含めることができるため、チラシの作成・ポスティング、パンフレット作成、看板製作などはそちらで計上することができます。
| 補助上限額 | 50万円 | 100万円 | 200万円 | 250万円 |
|---|---|---|---|---|
| 経費の総額 | 75万円 | 150万円 | 300万円 | 334万円 |
| ウェブサイト関連費 | 12.5万円 | 25万円 | 50万円 | 62.5万円 |
| ウェブサイト関連費以外の経費 | 62.5万円 | 125万円 | 250万円 | 271.5万円 |
申請時に必要な書類のそろえ方
書類は、公式サイトの公募要項を読んで、各様式の書類を用意します。申請書、事業計画書、宣誓・同意書、補助事業計画書(各種経費を計算したExcel)等をダウンロードして作成します。各様式に加え、申請枠ごとに必要な書類が異なります。
また、申請方法は【電子申請】を利用する場合、書類をExcelやPDFなどの電子フォーマットで用意する必要があります。
さらに申請書類一式を用意した後、地域の商工会議所に依頼すると、申請書に不備がないかどうかを確認した後に、様式4の書類を発行してくれます。
様式4は必ず必要になるため、できるだけ書類は早めにそろえて余裕を持って申請することをオススメします。商工会議所では、事業計画書へのアドバイスも受けることができます。
申請の流れについて
一般的な申請の流れは、次のようになります。
- ① gBizIDを取得する(約2週間)
- ② 必要書類を準備する(※申請枠によって、必要書類が異なります)
- ③ 近くの商工会議所に行って、紙で出力した申請書類一式を確認してもらい、「様式4」の書類を発行してもらう(約1週間)
- ④ 発行したgBizIDを使って、小規模事業者持続化補助金<一般型>の独自システムから申請を行う(第16回以降から郵送での申請はできなくなりました)。創業型の申請はjGrantsから申請。
- 事業計画書を作成した後は、中小企業診断士さんや専門家に確認してもらった方が安心です。
- 回号ごとに応募要項が異なり、難易度も上がっている傾向にあります。
事業計画書作成のポイント
小規模事業者持続化補助金には審査ポイントがあり、事業計画がポイントを踏まえているかどうかをチェックされます。さらに加点ポイントとなる項目があり、条件を満たすとさらに採択されやすくなっていきます。
公募要領に記載の内容です。申請する資格を満たし、計画に対して実行能力があるかどうかを見られます。
- 必要な提出資料がすべて提出されていること
- 「補助対象者」「補助対象事業」「補助率等」「補助対象経費」の要件及び記載内容に合致すること
- 補助事業を遂行するために必要な能力を有すること
- 小規模事業者が主体的に活動し、その技術やノウハウ等を基にした取組であること
事業計画の審査観点
- 自社の経営状況を適切に把握し、製品やサービス、強みについて適切に把握しているかどうか
- 経営方針・目標・今後のプランは、自社の強みを踏まえているか
- 経営方針・目標・今後のプランは、対象とする市場(商圏)の特性を踏まえているか
- 補助事業計画は具体的で、実現可能性が高いものになっているか
- 補助事業計画は、経営計画の今後の方針・目標を達成するために必要かつ有効なものか
- 補助事業計画は、小規模事業者ならではの創意工夫があるか
- 補助事業計画は、ITを有効に活用する取り組みが見られるか
- 補助事業計画に合致した事業実施に必要なものとなっているか
- 事業費の計上・積算が正確・明確で、真に必要な金額が計上されているか
ざっくりまとめると、「自分たちならではの強みを活かし、将来性のある事業計画になっているか、実現可能性が高いか、IT化や生産性向上につながっているか?」がポイントです。さらに、それにかかる費用に妥当性があり、必要不可欠であるということが伝わる内容だと採択されやすくなるということになります。
さらに、条件によって【重点政策加点】、【政策加点】からそれぞれ1種類を選択し、加点申請を行うことができます。事業計画に加え、加点審査も申請しておくと採択率が高まります。
ちなみに、公式サイトには業種別に作成された事業計画書の見本が置いてあります。こちらをご自身の事業に合わせてカスタマイズし、第3者が読んだときにわかりやすく計画が伝わるどうかもポイントです。
公式サイトに掲載中の事業計画の見本
公式サイトに事業計画の見本が展示してあります。「経営計画」のページから、8ページほどの計画を策定することができるため、基本的に8ページ用意する方が多いようです。
オンライン申請(電子申請)の利用方法
小規模事業者持続化補助金をオンラインで申請するには、事前に「gBizID」を取得する必要があります。gBizIDは、複数の行政サービスを同じIDとパスワードで利用することができるようになる認証システムです。(ID発行までに3週間程度かかるため、早めに登録しておく方が良いでしょう)
gBizIDを取得しておくと、小規模事業者持続化補助金以外にも、各種助成金・補助金等の申請にも利用できます。
gBizIDでIDを取得後、発行されたアカウントでログインを行って申請作業を進めます。PC操作が苦手な方には少しハードルが高いですが、項目にしたがって必要書類をアップロードしていくだけですので、操作自体は難しくないはずです。
jGrants(創業型):https://www.jgrants-portal.go.jp/
※第16回以降から郵送での申請はできなくなりました。
小規模事業者持続化補助金に申請する際の注意事項
オンラインで申請すると、公募締切り日前までに申請内容を修正することができます。経費項目などを採択された後に修正するのは大変ですので、最初に気を付けた方が良いことをピックアップしました。
どんな項目でも経費になるわけではない
補助金事業は、あくまで事業計画に従い、「対象となる経費」を使ったことを証明することで、補助金として受取ることができるものです。
申請した事業で発生する「必ず必要な経費」で、例えば一般的な事業に利用できる「自動車」「パソコン」「事務用品」などは、対象にならない可能性が大きいです。
経費項目に詳しい専門家に聞くか、事務局に問い合わせるなど、事前に調べておいて、問題がないかどうかを確認しておくと良いでしょう。
申請してから、入金完了までに1年近い時間がかかる
小規模事業者持続化補助金は、補助金の中では50~200万円の上限額で、規模としては大きな事業に該当しません。ですが、申請から採択、採択から実績報告、実績報告から入金、まで全体で約1年程度かかります。
採択後に、事業に対応してくれる事業者ともしっかり打合せを行い、かかる経費や項目について書類をしっかり用意してもらい、事業完了後も気を抜かず、最後の報告まで忘れないように対応していく必要があります。
また、経費を支払った後は、入金までに時間がかかるため、補助金をあてにするのではなく、事業計画ありきで運よく採択されたら補助してもらうくらいに考えた方が良さそうです。
採択されても「採択通知済み」になるまで、経費は使ってはいけない
申請した事業計画は、「採択」され、採択後に事務局から届く「採択通知済み(交付決定通知)」の状態になってからでないと、開始してはいけません。
「採択者一覧に掲載されていたので、早速ソフトウェアを購入した」場合、経費が却下される可能性が高いです。必ず、ご自身が「採択通知済み」を直接受け取った日付より後に、購入・契約手続き行いましょう。
小規模事業者持続化補助金が採択されたら?
小規模事業者持続化補助金に申請して採択されたら、提出した「事業計画」にしたがって事業を開始します。
申請書の内容に従って事業を実施する
採択されて実績報告するまでの期間は、約5ヵ月程度です。その間に、「事業計画」を進め、「経費」として申請した項目に対し購入や発注を行う必要があります。
経費項目として申請した項目は、「見積り書」「フォーマットに従った発注書または契約書」「請求書」「銀行振り込みの領収書」などが1つ1つの経費項目について必要になります。
また、ビフォーとアフターの写真が必要になるなど、採択後にそろえる書類も沢山あります。
着手のタイミングが遅れそうでも、早めに発注書等をそろえ、事業完了報告が間に合うように進める必要があります。
実績報告提出期限までに、実績報告を行う
事業が完了したら、原則「銀行振込み」でかかった経費を支払い、実績報告を行います。
実績報告(事業完了報告)は、採択回号ごとに締切りがあり、その期限を過ぎてしまうと補助金が受け取れなくなってしまうため注意が必要です。さらに、事業が最終提出期限よりも早く完了した場合、事業完了後30日以内に報告する義務があります。
実績報告のためにも「事業報告書等の書類作成が必要」になるため、あらかじめ何が必要かを確認しておき、書類が全てそろった状態で報告を行いましょう。
※補助事業実施期限は、事業報告の最終締切り日の10日ほど前になるため、それまでに事業を完了する必要があります。
「通知済み」になるまで差し戻しに対応する
jGrantsから実績報告をしてしばらく経つと、報告に対して事務局から差し戻しが来る可能性があります。不備がある箇所について、細かい指摘があるため、1つ1つ確認を行い、不備がないように書類を修正して再提出します。
「日付」「宛先」「書類のフォーマット」「報告した内容に記載がある文章や中身」など、小さな見落としに対してもチェックが入る可能性があるため、根気よく対応する必要があります。
補助金受給後にも報告義務が発生
実績報告完了後、差し戻しに対応してしばらくすると「通知済み」として、補助金の受給額が確定し、事務局から連絡があり、その後しばらくすると、受取口座に振込があります。
入金後、さらに1年ほど経過すると、また事務局から連絡があり、現在の事業の状況の報告を求められます。A4のWordファイルにレポート(様式第14)と直近の売上についての質問があります。対応にそこまで時間はかかりませんが、そういうものがある、と認識しておくと良いでしょう。
その他の助成金制度について
小規模事業者持続化補助金のほかにも、個人事業主、中小企業が利用できる補助金制度がいくつかあります。
ホームページ制作やネットショップ開業にも使える補助金は、次の3つです。上限金額、審査のために必要な書類や、申請するための条件もそれぞれに異なります。
| 補助金 | IT導入補助金 | ものづくり補助金 | 事業再構築補助金 |
|---|---|---|---|
| 対象 | ITツール導入やテレワークを行うための環境整備 | 革新的サービス開発・試作 品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資 | 思い切った事業内容の転換(オンラインサービスの導入等) |
| 条件 | 登録事業者が提供するIT化ツールを導入する必要がある | 付加価値のある事業計画 従業員の賃上げ計画 |
ポストコロナに向けて取り組みを行う企業 |
| 金額 | 5~450万円 | 750~2,500万円 | 500~7,000万円 |
| 補助率 | 1/2以内 | 1/2または2/3 | 1/2または2/3 |
それぞれ、事業規模や事業計画によって補助率や上限金額が変わってきます。また、補助金額が大きいものになると、中小企業診断士や行政書士などの専門家にも相談して、しっかりとした事業計画書を用意し、長期的に事業を進める計画を立てる必要があります。
早めに申請すれば、「もし不採択になった場合でも、また次の回に申請する」ということもできるため、専門家に相談しながら早めに用意して資金繰りに役立てましょう。
補助金申請に関して、EzONEでもご相談を承っております。
お気軽にご相談ください。→ お問い合わせ窓口