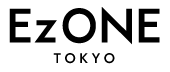新しくビジネスをスタートする際に、まずは「ビジネスモデル」や「事業戦略」について、具体的な方針を固める必要があります。この記事では、「BtoBとBtoCの違いについて」、それぞれの特徴についてまとめました。
目次
BtoBとBtoCのビジネスの違い
ビジネスは、一般的に「BtoB(Business to Business)」と「BtoC(Business to Consumer)」の2種類で区分けして考えられます。前者は「企業:企業」、後者は「企業:一般消費者」です。
大きな違いは、BtoBが「1:1」の関係であるのに対し、BtoCは「1:N(複数)」の関係になるところです。
BtoBビジネスの考え方

BtoBビジネスは「専門性の高いサービス」を提供すること、が前提にあります。事業形態が「法人」である必要はなく「個人」で商品販売やサービス提供をすることも可能です。特徴としては、下記のようなものがあります。
(BtoBビジネスの特徴)
- 高度なレベルの作業を求められる
- 特定分野における専門性が必要
- 実績や過去の経験、取引先も判断される
- 設備投資が必要な場合もある
(事業者同士の関係性について)
- 相互のビジネスマッチングが必要
— 思考や需給が一致する必要がある
— 専門的な相互理解がない場合でも、どちらかにノウハウがあれば対応できる
— 事業内容によって、決裁者が変わる
- 人間関係も求められる(ビジネス単独の利害一致だけが条件ではない)
- 決裁者単独の意思決定だけで物事が進まない場合もある
基本的にBtoBビジネスの場合、組織同士がつながり、「どちらかが持つ特技や設備・機能等を使って、お互いの(どちらかの)生産性を高めるための取引を行うこと」がベースになります。
決裁者が「代表取締役」のこともあれば、組織規模が大きい場合「プロジェクトマネージャー」「採用担当者」など、決定権を持つ人間が変わる場合もあります。また、組織規模が大きい場合、稟議を通す必要などもあり、組織全体での規定があるなど、仕組みが少し複雑になることもあります。
中小企業などのオーナー経営者が個々に取引を行う場合は、株主などのステークホルダーの影響を受けにくく、BtoCに近い感覚で取引が成立することもよくあります。
BtoBのビジネスモデル例
BtoBビジネスの全体図を、ある特定の産業の中で考えてみます。下図は、自動車産業の中で、車を製造し、販売する一連のフローです。

自動車を販売するためには、「自動車を組み立てるための素材を用意し(部品メーカー)(金属メーカー)」「自動車を生産し(自動車メーカー)」「自動車をエンドユーザーに販売し(販売代理店)(直営店)」「自動車の付帯サービスを販売する(自動車保険)(カーメンテナンス)(車検)(緊急対応)」という、一連のフローが存在します。
誰がどの事業領域を担当し、どのエリア(地域)で活動を行うか?また具体的にどういった方針で進めるのか?は、最初から決まっているものではなく、企業間で業務提携を行い、個々のルールに従って個別に対応を行っていくという仕組みの中で動いています。
この全体の仕組みの中で、自分自身が提供できるサービスは何か?を考えることがビジネスモデルの策定です。実際にサービスを提供するとなると、資材の調達や設備、人材も必要になるため、初期投資も運転資金もかかります。
ビジネス(事業)は「売上を立てること」が前提ですので、ビジネスモデルを考える際は、取引先を意識して、どのくらい経費がかかって、どのくらいの売上が見込めるか、を考慮しながら、実際に取引を行っていくことが大切です。
BtoCビジネスの考え方

BtoCビジネスは、BtoBビジネスで行った一連の事業フローの中で、量産可能なものをパーツ化し、求め安い価格で一般消費ユーザーに届ける形のビジネスです。
BtoBの場合、「個別にカスタマイズ」が発生しますが、BtoCの場合、「決まった形」の商品やサービスであることが多いです。
薄利による量産体制が必要になるため、個人事業主がBtoCビジネスに対応しようとすると、1:N(複数)のバランスが難しく、継続が大変なビジネスモデルになると思います。(飲食店・小売・消費者向けサービス等の実体があるもの)
BtoCビジネスで利益を増やすためには、量産体制を作るところが大切になります。
(BtoCビジネスの特徴)
- BtoBで提供されるサービスをフォーマット化したもの(設計図を元に量産されたもの)
- 顧客単価が安価な場合が多い
- 不特定多数に向けて販売される
- 個別対応はほぼしない
- 問い合わせ窓口などのカスタマーサービスも必要
- 利益を増やすためには、量を稼ぐ必要がある
- ユーザー(個人)の意志や感情が影響する
一見、「安価な品物や、決められたサービス」を扱っているため、参入障壁が低く事業を始めることが簡単そうに見えるビジネスモデルですが、「儲ける」という観点で見ると、量を提供する必要があり個人で行うには難しいと思います。
量産するために、ひたすら回転率を良く、資金を継続させながら、事業を回していく必要があります。
情報商材の場合、個人でもBtoCビジネスは実現可能?
情報商材など、無形の商材を販売する場合、「フォロワー」「セミナー参加者」「閲覧者」「購読者」など、1:N(複数)の関係が構築しやすい場合があります。情報には拡散性があり、顧客の手元に届けるのに物理的な作業が必要ないため、薄利多売の体制を作ることが可能です。
例えば、YoutubeやTikTok、Instagramなどでチャネルを作りフォロワーを増やしたり、ビジネスセミナーや経営塾などの情報商材を使って参加者を集めたり、ブログ記事を量産して閲覧者を増やすなどの方法が考えられます。数字を集めるためには労力がかかりますが、個人規模でBtoCに対応するには、無形商材が1番取り扱いしやすいモデルになるかと思います。
多くのビジネスが、3年以内に廃業することになってしまう理由は?

起業して3年以内に廃業する人は20%といわれています。理由として考えられることは、自分自身が行うビジネスについて検討しないまま「なんとなく周りの人を見よう見まねで事業をスタートし、聞いた情報を元に判断して、継続することが困難になるから」だと考えられます。
ビジネスは売上を作るための活動なので、シンプルにとらえると物事はわりと単純です。
多くの人は、起業前の会社雇用によって「1日働いたら●●円貰える」→「月で計算すると●●円」という感覚がしみ込んでいるため、「ビジネスモデル」を検討して、このビジネスモデルを動かすにはどうしたらいいか?を考える作業が苦手かもしれません。
事業を継続させるために、資金がいくらあれば大丈夫かを逆算して計算する
収入と支出の計算ができないと、手元にある資金をうまく使って事業を回すことが難しくなっていきます。まずは最低ラインを決めて、最低でもこの売上がないと、事業を継続することが難しい(生活することが難しい)、というのを計算することが大切です。(月に20万は生活費に必要。経費としてかかる支払い、設備投資、仕入れ、税金やローン返済にいくら必要。→ だから、売上はいくら必要)
- 生活費(家賃・食費・保険・年金・その他)
- かかる経費(人件費・設備投資・仕入れ・光熱費・税金)
- 必要な売上(生活費と経費を足したもの)
これだけ計算できれば、あとは売上を伸ばすための方法(やり方)を検討し、かかる経費を節約しつつ、サービスの品質を高めるための方法を検討していくだけになります。
筆者が個人的に良くないと思うのは、「怪しいビジネスコミュニティに参加すること」「ビジネス書を読んで理解した気持ちになってしまうこと」です。正しい情報を正しく教えてくれる人はあまりいません。自分自身のことを1番理解しているのは自分自身(または身内)であることが多いため、自分自身でしっかり考えることが大切だと思います。
PDCAを回してより良いビジネスにしましょう

ビジネスモデルの検討と自己分析を行い、他者とコミュニケーションをとることで、少しずつ結果が変わってくると思います。そんなに一生懸命自分自身を売り込む必要もなく、買ってくれる人がそれなりに満足して、それなりに楽しく過ごせるようになっていくでしょう。
世の中のメディアが発信する情報に不安になったり、目立つ人の発言が「正しいもの」と誤解してしまうこともよくありますが、そうではなく、自分の在り方と向き合って、シンプルにとらえるとそう不安にならず、少しずつ進めることができるはずです。
ビジネスは、1にも2にもキャッシュフローの管理が大切ですので、そこを踏まえたうえで、BtoBとBtoCビジネスの違いを理解しつつ、ブラッシュアップにつなげてください。